奥多摩の釜飯屋

奥多摩にひっそりと建つ民家で食べる釜飯の味は格別である。
少し風は冷たくなってきたけれど、秋の晴天に誘われて、ひさしぶりに
奥多摩に行ってみようという気になった。車も快調である。
釜の淵公園で散歩をしてそれから川井から山の道をのぼって
11時半ころめざす釜飯屋についた。ところが、すでに門前には
行列ができている。
.このあたりは、少し前までは「隠れ家」と呼ぶにふさわしい静かな雰囲気を
もっていた。但しこれは1945年から5-6年続くベビーブーマー世代が
定年退職をして ひまなジジババが殺到する前の話である。
なにしろ、当時は毎年250万人のベビーが生まれた。ちなみに
現在は100万人になるかならないかといったところであり、この
人達が60歳定年を迎えた第一陣が2005年ごろから世に放出され
はじめ、その頃から 隠れ家が隠れ家ではなくなってきたのである。
そのことをすっかり失念していたため、せっかく早めに行ったのに
30分も待たされることになった。
しかし待たされて食べた鳥釜飯はさすがにうまかった。
一杯一杯また一杯
友人がフェルメールとレンブラント展を見たあと、森ビルの52階から
眼下の街並みを見て、頭に浮かんだ李白の7言絶句をメールして
来ました。(黄鶴楼にて孟浩然の広陵にゆくを送る)
故人西辞黄鶴楼 故人西のかた 黄鶴楼を辞し
烟花三月下揚州 えんか三月 揚州にくだる
孤帆遠影碧空尽 こはんの遠影 碧空につき
唯見長江天際流 ただ見る 長江の 天さいに流るるを。
親友の孟浩然が揚子江を下ってゆく情景を詠んだものです。
孟浩然と言えばあの有名な五言絶句(春暁)
春眠不覚暁 春眠 暁をおぼえず
処処聞啼鳥 処処に ていちょうを聞く
夜来風雨声 夜来風雨の声
花落知多少 花落つること 知りぬ多少ぞ。
そして更に李白の七言絶句(山中幽人(ゆうじん)と対酌す)
両人対酌山花開 両人 対酌(たいしゃく) 山花開く
一杯一杯復一杯 一杯 一杯 また一杯
我酔欲眠君且去 我(われ)酔いて 眠らんと欲す 君しばらく去れ
明朝有意抱琴来 明朝 意あらば 琴(きん)を抱きて来たれ
筆


30年以上も前のこと、 新宿だったか新橋だったか忘れてしまったが、
地下に下りる階段の途中にちょっとした広場があって、そこで中国の
物産展のような小規模な店舗があった。 何の気なしに寄り道をして、
どういうつもりかも覚えていないが、一本の筆を買った。高校以来、下手の
横好きで水彩を時々描いていたので、多分水彩用の絵筆にしてみるつもりだった
のだろう。値段が 3000円と当時の中国製品としてはかなりの高値と思った
ことだけは覚えている。
ところが、家に持って帰って実際に使用してみると、太線 細線思いのまま、
水をたっぷり含んで垂れることなく、柔軟な筆先ながら弾力性に富んでいて
素人にも名品であることがわかった。試しに字を書いてみると、習字など
小学生の時以来経験がないのに、筆が走るというか、それなりの字に
なっているのであった。
その後仕事が忙しくなって、しばらく筆を使用しなくなり、すっかり
筆のことは忘れていたが、15-6年たってからあの筆の事を
想い出して探し当てたところ、筆の付け根の竹に割れ目が入っていること
に気が付いた。 糸を巻いて補修をしたままにしておけばよかったものを、
その上に接着剤をつけたのが大変な失敗だった。 筆毛の部分は慎重に
避けて、穂先を上に向けて置いたのだが、翌朝筆の半分が接着剤で固まって
いるのに気が付いた。 どうやら竹の割れ目の部分から毛細管現象で
接着剤が上の毛の部分に浸透したようである。ほぼ半分毛先を切り取っても
まだ普通の筆よりは手になじんだが、さすがに満身創痍の姿で、気の毒
になり、使い勝手も複雑になってとうとう使わなくなってしまった。
その後、中国や香港に行った時にも、同じような筆を探して何本か購入したが、
外見は同じでも似て非なるものばかりで、決して見つかるものではなかった。
今でも不思議な筆だったと思う。たまたまたくさんの筆を製造している中で
偶然出来たものなのか、それともすばらしい達人が居てそのノウハウや
永年の技術を十分に発揮してつくりあげた逸品だったのだろうか?
奈良に都が出来る400年も前に王義之が出て今でもその書を日本の書家が
手本にしている国である。 その歴史の重みを考えると、私はやはり、当時
練達の人がいて その人が造ったものだったと思う。 半分になって
しまった筆をよく観察するとやわらかい毛の中に短くて多少固い穂先が白い
毛が混じっているようである。
マジョーレ湖 (北イタリア)
1971年のキラキラ光っていた夏、夢のような湖を見つけた。
2014年再訪して仲間と離れ、1人で湖の周りを逍遥した。
湖に近いベンチに腰をおろして、正面に見える森とお城を
スケッチしていると、隣に座ってしばらくそれを見ていた老夫婦
のうち、おばあさんが 「それを売って頂戴」と声をかけてきた。
聞いてみると、オランダ人で観光で来ているとのことであった。
実を言うとこんな経験は初めてだったので、心の準備が出来て
いなかった。 第一値段をどうつけたら良いのだろうか?第二に
実はお城が森に沈み込んでいて、構図が気に食わなかったので
こんな絵を売って良いのだろうか 第三に安値で買いたたかれる
のもいやだな などなど。

面倒なので 「あまりいい絵ではないので」などと言って断って
しまい、後で大いに後悔した。 相手が望んでいるのに断るのは
無礼ではないか。
そこで団体で同行していた某美術団体のえらい方に、「どうすれば
良かったのでしょう」と聞いてみた。
すると 「住所氏名を書いて無料で差し上げれば良かった」 そして
冗談を言う顔つきになって「もしかするとそのうち遺産がどっさり寄贈
されることもあるかも」と言った。
私はあと何年生きられるのだろうと思った。
そして絵を続けるのも悪くないなと思った。
①デュッセルドルフ
Duesseldorf
当時の気分を味わいたいと思い、3日間アパートをレンタルしました。
しかし 短期旅行にはやはりホテルの方が便利です。小さな業者
なので、駐車場が小さくて車が入らず離れた一般の、駐車場まで
荷物をもって歩いたり、朝食のためにスーパーであわただしく買い物を
したり、あげくのはてにオートロックの部屋で鍵を閉じ込めてしまったり
無駄な時間を過ごしたと思います。
当時との違いは 街全体が汚くなったこと。住宅街の公道のあちこちに
巨大なゴミ箱が置いてあること。 昔は道端のどこに駐車しても良
かったのに、殆ど東京と変わりなくなった。売店のお姉さんから「ニーハオ」と
声をかけられたこと。などなど。
スーパーが出来ていて、しかもカートには鍵がかかっており、1ユーロ入れて
鎖からはずさなければなりません。この1ユーロは買い物が終わって
カートを鎖につなぐと返却されます。それを知らずに返却に来たおばさん
のカートを受け取ろうとしたら睨まれました。 ドイツのおばさんは怖い
ですから。 いや日本のおばさんの方がもっと怖いかな?
方が
② ツォンス
Zons
デュッセルドルフの10キロばかり南にZonsという城壁でかこまれた小さな
町があり冬枯れの景色などが良かったので、よく遊びに行ったところでした。
かなり観光化していましたが、レストランなど昔のままでした。
③ ゾーリンゲン
Solingen
デュッセルドルフの近くにゾーリンゲンという刃物で有名な町があり、そこに
Schloss Burg というお城があります。
SchlossもBurgも「お城」という意味なので、 猫に「ネコ」という名前を
つけたようなものかなと常々思っていました。
④ローテンブルグ
Rothenburg ob der Tauber
おなじみの大観光地です。この鍛冶屋の建物、30年前はまわりの城壁の
上から描いたのでしたが、今回は下から描いていると、しばらくして3階の
窓が開いておばさんがタバコの吸い殻をぽいと捨てました。
⑤フュッセン
Fuessen
フュッセンのHotel Christine オーナーのおじさんが
荷物をもって階段をのぼりながら、このホテルを妹の
Christineと一緒にやってきたが、その妹が亡くなって
しまったと言いました。 3階の真ん中の部屋のバルコニーから
ノイシュバンシュタインが良く見えます。
東山魁夷が生前3度ほどこの部屋に泊まったとのことでした。
絵を志す者にとって画壇の巨星の座ったであろう椅子にすわるのは
心躍る出来事でした。
後にフォルゲン湖のオペラハウスから対岸をみたら、東山魁夷
の絵によく出てくる風景に出会いました。山の中腹にノイシュバン
シュタイン城が見えています。
⑥コロマン教会
St.Coloman
ノイシュバンシュタイン城の窓から小さく見えていました。
草原の中に建つ可愛い教会です。
周りを2-3回車でまわって、道端に車を止め、フロントグラス越しに
スケッチをしました。
このあと、背景に見えている山の後ろにまわって リンダ―ホフ城に行きましたが
オーストリーに迷い込み、ナビの切り替えに手間をとりました。
⑦ボーデンゼー
Boden See
フュッセンから次の宿泊地ラインフェルデンに移動する途中、
Pilgerhofの庭で野菜とソーセージの簡単な昼食を摂りました。
後にボーデン湖が広がり、快晴でとても気持ちのよいところでした。
⑧ゼッキンゲン
Saeckingen
上流のライン川かかる屋根付き橋です。
道路脇の石に腰を下ろしてスケッチをしていると、猫が妙親しげに
すり寄ってきました。手前がスイスで対岸がドイツです。
⑨コルマール
Colmar
バーゼルの美術館でモネの作品の展示を見た後、アルザス地方の
コルマールに行きました。
⑩カイザースベルグ
Kaysersberg
フランス領なのでケゼルスベールと読むのが正しいのかもしれません。
アルバート シュヴァイツアー博士の生家が博物館になっています。
屋敷の中庭です。 左側の階段を上ると小さな教会になっており、
シュヴァイツアー博士が弾いていたオルガンがあります。
⑪シュヴェービッシュハル
Schwaebisch Hall
塩の取引で栄えた町です。 コッハー川にかかる屋根付き橋が
中世の面影を残しています。
ここにはゲーテインスティチュートがあってドイツ語を学ぶ日本人も
ときおり見かけられるようです。
ひなげし

ひなげし
ロンドンの西100km余りに自然保護地区がある。
17世紀の景観をのこしており、英国人の心のふるさととして
愛されている場所である。
うらうらとした日差しのもと、案内人について遊歩道をのんびり
歩いていると、白鳥のいる小川を過ぎたあたりの麦畑に 楚々とした
ひなげしの赤がところどころに顔を出している。
こんな時はきっと昔習ったあの詩を想い出すのだ。
Pippa's Song
Year's at the spring,
And day's at the morn;
Morning's at seven;
The hill-side's dew-pearl'd;
The lark's on the wing;
The snail's on the thorn;
God's in His heaven-
All's right with the world!
時は春
日はあした
あしたは七時
かたおかにつゆみちて
あげひばりなのりいで
かたつむり枝に這ひ
神そらにしろしめす
すべて世はこともなし



ひなげしで想い出したが 一人の味方も無くなった時に「四面楚歌」という。
漢の劉邦と楚の項羽が天下を争った。 はじめのうちは項羽が勝ったが、
補給線が延びすぎてとうとう 垓下(がいか)というところで包囲されてしまった。
夜になって四方から楚の歌が聞こえる。
これを聞いた項羽は、楚が負けたので、楚の人間が漢の部隊に加わった。
自分は裏切られたと思った。
しかし楚はまだ漢に攻められず、楚の人間も項羽を裏切ってはいなかった。
漢の参謀長の張良が 楚の歌を知っている部下を集めてあちこちで楚の歌を
歌わせた謀略に項羽はひっかかったのであった。
この時の項羽の詩
「力山を抜き、気は世を蓋う。
時、利あらず 騅(すい)逝かず
騅の逝かざるを如何にすべき
虞や虞や汝を如何せん」
騅は彼の愛馬、虞はかれの愛人である。
項羽はここで愛人の虞美人を殺したのち
囲みを破って逃れ烏江というところで自殺した。
虞美人が殺されて血を流したあとから、赤い花が咲いた。
それがヒナゲシであり、虞美人草ともいう。
この話は 渡辺紳一郎の「東洋語源物語」に出ている。
この国の話は血なまぐさいですな。
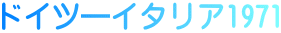
1971年夏 デュッセルドルフを起点にイタリアに自動車旅行をしました。
8月13日
Duesseldorf出発 7:40
デュッセルドルフ ベルリナー通り 1971夏
Baden Baden 12:15
Basel .................................15:30
Murten............................. (泊)
8月14日
Murten 出発.................8:07
Montreax.........................9:52
Sillon (シヨン城).........11:52

シヨン城は英国の詩人バイロンが訪ねたというレマン湖畔のお城です。
St.Niklaus -Zermatt-Gornergrat -Zermatt-StNiklaus (泊)
車を St.Niklausに置き、 ツェルマット(標高1604m)からは登山電車に乗って
ゴルナグラート(標高3089m)に行きました。 よく晴れた日で マッターホルンや
モンテローザががよく見えました。
ツェルマット駅
8月15日
St.Niklaus出発 ..................13:55
Zug..........................................14:30
Stresa.....................................16:25
Stresa(船)...............Isola Bella.....Stresa(泊)
.
ミラノの北部 マジョーレ湖に浮かぶ イゾラベッラ 偶然この夢のような島を発見して
居合わせたイタリア人の家族と一緒に小舟に乗って 午後の島に行きました。
この旅行のまさにハイライトになって、一生忘れられない体験になりました。
たまたま湖畔のStresaに宿を見つけて 翌朝も島に行って見ました。
8月16日
Stresa 出発 ................. 11:10
Ascona ................................ 12:50
Airoro.................................... 14:45 アルプスのてっぺんの道でオーバーヒートでエンストをしました。
Zug ................................... ..17:50 (泊)
8月17日
Zug 出発 .......................8:05
Luzern .................................8:50
Basel ....................................11:20
Frankfurt..............................16:00
Duesseldorf........................18:00 (帰着)
車は当時60万円で購入した中古のアルファです。 前の持ち主が相当荒っぽい
運転をしたらしく、かならずどこか故障をする代物でした。
アルプスでオーバーヒートをした経緯は以下の通りです。
当時St.Gotthard(峠)をスイスからイタリアに抜けるには、山の上を
通るかGoeschenからAiroloに通じる15キロメートルのGotthard
rail tunnel をPiggy backで通過するしかなく、往路は無事に通過出来た
のですが、帰路はトンネルの中で事故があって不通になり、やむを得ず
高度2100メートルの峠越えをせざるを得なくなったためでした。
Piggy backというのは 無蓋貨車に車で乗りこみ、運転者はそのまま
ブレーキをしっかりかけて7-8分、貨車がトンネルを通過するのを車中で
待つ方式です。 その後、1980年にGotthard road tunnel が出来て
車で通過可能となり、現在rail のほうはトラックが主に利用している
模様です。
ついでに車の始末ですが、友人に20万円という約束で譲って帰国
した後、5万円を送金してくれたあとで、エンジンオイル不足の警告ランプが
点灯しているのにアウトバーンを時速200キロで走り、エンジンが爆発して
分解してしまったとのことで、あとの15万円は回収不能となりました。
ともあれ人身事故がなかったのが不幸中の幸いでした。
================================= ====================================
シヨン城撮影
ニコンF レンズ ニッコール 1: 1.4 f=50mm
ニッコール 1: 3.5 f=40mm~86mm) によります)
======================================================================








